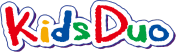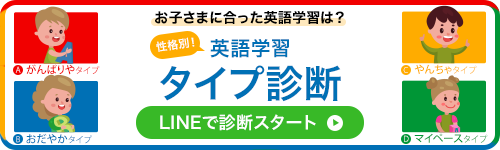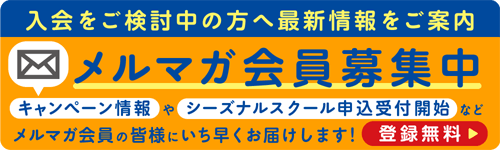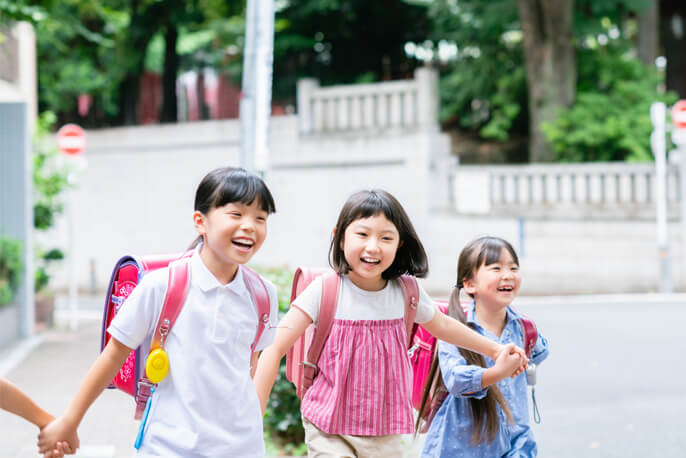
「小学生の放課後の過ごし方にはどのような選択肢がある?」「共働き家庭でも安心して預けられる場所は?」などと悩んでいる方も多いでしょう。
小学生の放課後の過ごし方には、学童保育、習い事、自宅での留守番などさまざまな選択肢があり、家庭の状況や子どもの成長に合わせて選ぶことが重要です。特に、共働き家庭では、安心して預けられる環境の確保が求められます。
本記事では、放課後の代表的な過ごし方5選や学年別の変化、親が抱える不安の解消法を解説します。小学生が放課後に安心して過ごすためのヒントが満載なので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
1.小学生の代表的な放課後の過ごし方5選

小学生が放課後にどのように時間を過ごすかは、家庭環境や学年によって異なります。放課後の過ごし方は、昔から大きな変化はありません。しかし、時間の使い方には現代ならではの特徴があります。
ここでは、小学生の代表的な放課後の過ごし方として5つの選択肢を取り上げ、それぞれの特徴と注意点などを具体的に解説します。
1-1.学童(放課後預かりサービス)を利用する
共働き家庭の小学生は、放課後に学童保育を利用していることが多いです。特に小学校低学年の子どもは自分で時間管理が難しいため、安全かつ有意義な時間を過ごす場として多くの家庭で利用されています。
学童保育では、親が帰宅するまでの間、子どもが一人で過ごすリスクを軽減しつつ、他の子どもたちと一緒に過ごせる環境が整っています。たとえば、学童保育では宿題のサポートやレクリエーション活動を通じて、放課後の時間を単なる「待ち時間」にしない工夫がされています。
また、自治体が運営する公設学童だけでなく、民間のプログラムも増えており、学習に特化したものからスポーツ重視の施設まで幅広い選択肢があります。選ぶ際には、施設の方針や運営時間、子どもの興味関心などを考慮して決めるようにしましょう。
学童保育は子どもの成長だけでなく、保護者の安心感を支える存在です。そのため、家庭のニーズに合わせた最適な学童保育を選ぶことの重要です。
なお、学童保育の詳しい情報や選び方については、「学童の定義・種類とは?子どもは結局どこに預ければいいの?」で詳しく解説しています。
1-2.自宅で過ごす
放課後を自宅で過ごす子どもの数は、特に高学年になるにつれて増加傾向にあるでしょう。留守番を選ぶ理由としては、学童保育を利用できない、子どもが一人で過ごすことを望むといったケースが挙げられます。
子どもが自宅で留守番をする場合は、ゲームや漫画、動画を視聴するなど、自分の好きな方法でリラックスした時間を過ごすことが可能です。
しかし、自宅での留守番は、子どもにとって自立心を育む場にもなりますが、親の管理が欠かせません。防犯対策や時間の使い方に注意しながら、子どもが安心して過ごせる環境を整えましょう。
1-3.友達と遊ぶ
小学生の放課後の過ごし方として、友達と遊ぶことも定番でしょう。友達の家でおもちゃやゲームで遊んだり、一緒に宿題をしたりと、学校とは違う環境でのびのびと時間を過ごせます。
友達の家に遊びに行くことのメリットは、学校以外の場でのコミュニケーションが深まる点です。同じ遊びを共有することで、友情が育まれるだけでなく、相手の家庭のルールを学ぶ機会にもなります。
また、室内遊びを中心にする場合もあれば、友達と一緒に出かけるなど、活動の幅も広がります。インターネットが普及した現代では、自宅にいながらオンラインゲームを通じて友達と一緒に遊ぶこともあるでしょう。
1-4.習い事に通う
習い事も、放課後の過ごし方として人気の高い選択肢です。音楽やスポーツ、学習塾など、子どもの興味や才能を伸ばす場として多くの家庭が取り入れています。
習い事を取り入れることで、子どもは新たなスキルを獲得し、成長につながるでしょう。
しかし、時間の使い方を誤ると、宿題や休息の時間が不足する恐れもあります。子どもの体調や学校生活とのバランスを考慮しながら、スケジュールを調整しましょう。
なお、習い事の選び方や人気の習い事については、「【小学生に人気の習い事とは?】習い事の選択ポイントや注意点を紹介!」で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
1-5.公園で外遊びをする
公園は、子どもたちの創造力を育む放課後の定番スポットです。人気の遊具で遊んだり、一輪車や縄跳びで技を競い合ったり、友達とごっこ遊びを楽しんだりと、子どもたちは限られた空間で工夫を凝らして遊んでいます。
単に体力がつくだけでなく、自然との触れ合いや、即席でルールを決める協調性の向上も外遊びのメリットです。たとえば、鬼ごっこやボール遊びなどの集団活動では、瞬時の判断力やチームワークが鍛えられます。
一方で近年の公園では、ボール遊びが禁止されたり、安全性の観点から遊具が減少したりするケースも少なくありません。このような状況を受けて、公園に集まった子どもたちがゲーム機や漫画を持ち寄って静かに過ごすなど、新しい遊び方も生まれてきています。
2.【学年別】放課後の過ごし方の変化

小学生の放課後の過ごし方は、成長段階や生活環境によって徐々に変化します。低学年では保護者のサポートが不可欠ですが、学年が上がるにつれて自立心が芽生え、選択肢も広がります。
また、学習面や遊びの内容も発達に応じて変わるため、親はその変化に対応しながら適切にサポートすることが重要です。
以下では、小学1〜2年生、3〜4年生、5〜6年生の段階ごとに、放課後の過ごし方の特徴を解説します。
2-1.小学1~2年生の過ごし方
小学1〜2年生は、親や保護者のサポートが欠かせない時期です。時間管理や自分で判断する力が未熟なため、基本的には学童保育や親が関与する習い事など、管理された環境で過ごす傾向にあります。
一方で、低学年の子どもにとって放課後は、学校での疲れをリフレッシュする時間でもあります。体を動かして遊んだり、友達と一緒に過ごしたりすることで成長を促すことにもつながるでしょう。たとえば、学童保育では宿題をするだけでなく、自由時間に他の子どもと遊ぶこともできるため、バランスよく時間を使えます。
1~2年生は自宅での留守番はリスクが高いため、安全対策や見守りが必須です。また、放課後の活動が多すぎると疲れが溜まるため、休息時間もしっかり確保する必要があります。
2-2.小学3~4年生の過ごし方
小学3〜4年生になると、ある程度の自立心が芽生えるため、親がすべてを管理しなくても、自分で遊びや活動を決められるようになります。この時期の子どもは、友達と公園で遊んだり、習い事に積極的に参加したりする機会が増えるのが一般的です。
さらに、学童保育の利用割合は小学4年生から大きく減少する傾向があり、放課後を自宅で過ごすケースが増えていきます。習い事や友達との遊びを中心に放課後を過ごす子どもも増えるでしょう。
一方で、友達との付き合いが増えることで、トラブルのリスクが出てくる時期です。たとえば、遊びのルールをめぐる問題や、ゲームに熱中しすぎるなどのケースが考えられます。親は適度に子どもの放課後の活動を把握し、必要に応じてフォローすることが重要です。
2-3.小学5~6年生の過ごし方
小学5〜6年生になると、放課後の過ごし方がさらに多様化し、親の関与が少なくなります。高学年の子どもは、放課後に自宅で留守番をしたり、友達と外で遊んだりする機会がさらに増えます。また、習い事に打ち込んだり、学習面での遅れを懸念して塾に通い始めたりする子どもも増えるでしょう。
この時期は、学校の勉強や習い事などに追われることが多くなるため、放課後の時間を有効に使うことが大切です。また、思春期特有の悩みも出てきます。親は子どもの変化に注意し、必要に応じて相談に乗れる体制を整えておくといいでしょう。
小学5〜6年生は、自立した行動と責任感を身につける重要な時期です。親は遠くから見守りつつ、必要なときにアドバイスできる環境を整えましょう。
3.放課後の過ごし方に関する親の不安と対策

子どもの放課後の様子を把握し、適切にサポートすることは、保護者にとって重要な課題です。日々の生活で感じる不安や悩みに対して、実践的な解決方法を知ることで、子どもの健やかな成長を支えられるでしょう。
以下では、代表的な不安とその対処法について、具体的な解決策を提案します。
3-1.子どもが一人で家にいるのが気がかり
親が不安に感じる代表的なケースとして、子どもが放課後に自宅で一人で過ごす場合が挙げられます。特に低学年のうちは、危険な状況に対応できないことや、知らない人が訪ねてきた際のリスクが心配されます。鍵のかけ忘れやインターホンへの対応など、ささいなことが大きな問題につながる可能性もあるでしょう。
不安を軽減するためには、あらかじめ「訪問者には応答しない」「親に連絡する」などのルールを決めておくことが重要です。また、防犯グッズの設置や見守りサービスの利用もおすすめです。
子どもが安全に自宅で過ごせる環境を整えることで、親の不安も減らせます。日々のコミュニケーションを通じて、緊急時の対処方法を確認しておきましょう。
3-2.放課後に遊びすぎて宿題が進まない
子どもが放課後に友達と遊びすぎてしまい、宿題を後回しにすることも親の不安の一つです。特に、小学校中学年から高学年にかけては、遊びたい気持ちが強くなり、家庭での学習がおろそかになるケースも増えます。
解決策として、家庭内で「宿題をしてから遊ぶ」というルールを決めるといった工夫をしましょう。基礎的な学習習慣を早い段階で身につけることで、子どもの学力向上につながります。また、学童保育や習い事のなかで宿題を済ませられる環境を選ぶのもおすすめです。
遊びと学習のバランスを取ることが、子どもの健全な成長を支えるポイントです。日々の習慣づけを通じて、自分で時間管理ができるようサポートしましょう。
3-3.スマホやゲームに依存しそう
現代の子どもたちにとって、スマホやゲームは非常に身近な存在です。適度な視聴は、子どもの不安や孤独感を和らげる効果もあります。
ただし、使用時間や内容については親の管理が欠かせません。制限を設ける際は、禁止事項を列挙するのではなく、「テレビアニメは1時間まで視聴できる」など、許可される範囲を明確に示すことが重要です。また、制限の理由を子どもにわかりやすく説明し、同意を得ることで、隠れた使用を防げます。
スマホやゲームは適度なルールのもとで使用すれば、リフレッシュの手段となります。親子で話し合って一緒にルールを決めたうえで、適切に使うようにしましょう。
3-4.遊び相手の保護者と連絡が取れない
子どもが友達の家で遊ぶ場合、遊び相手の保護者と連絡が取れないことは親にとって大きな不安材料の一つです。約束の時間になっても子どもが帰宅しないと、何かトラブルが起きているのではないかと心配になってしまうこともあるでしょう。
この不安が生じる背景には、親同士の事前連絡が不足していることや、緊急時の対応方法が決まっていないことが考えられます。対策としては、日頃から子どもと話をする時間を設け、誰と遊んでいるのか、どこで過ごしているのかを把握することが大切です。
また、機会を見つけて友達の保護者と挨拶を交わし、連絡先を交換しておくことで、緊急時や問題が発生した際にスムーズな対応が可能になります。可能であれば学校や地域の行事に積極的に参加し、保護者間のつながりを深めておくのもおすすめです。
3-5.寂しい思いをしていないか
子どもが一人で過ごす時間の寂しさも、保護者にとって大きな心配事の一つとなっています。子どもの心の健やかな成長には、充実した交友関係や楽しい時間の共有が欠かせません。
現代はオンラインコンテンツで時間を過ごすことはできますが、それは必ずしも子どもの感情的な満足につながるわけではありません。たとえ退屈しない環境が整っていても、子どもが本当の意味で楽しく過ごせているかどうかは別の問題です。
子どもが感じる寂しさにいち早く気づけるよう、保護者は普段から子どもの表情や言動に注意を払い、心の変化を見逃さないようにすることが大切です。また、家族で過ごす時間を意識的に設けることも、子どもの情緒面のサポートにつながります。
4.小学生の放課後の過ごし方に関するよくある質問

小学生の放課後の過ごし方に関して、特に初めて子どもが小学校に上がる家庭では多くの疑問や不安が生じます。下校時間や学童保育の利用条件、共働き家庭での習い事の両立など、親が知っておくべき情報はさまざまです。
ここでは、よくある質問に対して具体的に解説し、疑問の解消をサポートします。
4-1.小学1年生の下校時間は何時くらい?
授業時間の基準は文部科学省によって定められており、1コマ45分が基本です。下校時間は、各学校の状況により若干の違いが生じる可能性があります。
小学1年生は5時間授業のため、下校時間は一般的に14:00〜15:00頃になります。地域や学校によって多少の違いがあるため、入学前に確認しておきましょう。ただし、入学して最初の2週間ほどはまだ給食が始まらず、午前中で授業が終わることが多いため、12:00〜13:00頃に下校するケースが一般的です。
小学1年生の下校時間は想像以上に早いため、事前にスケジュールを調整し、子どもの放課後の居場所をしっかり確保することが重要です。
4-2.4年生以降は学童保育に入れないの?
現在の学童保育制度は、小学校1年生から6年生までの児童を対象としています。しかし、施設の収容能力や職員数の関係で、多くの学童保育では低学年の受け入れを優先する傾向にあるのが現状です。
厚生労働省の令和4年の統計によると、学童保育の利用率は学年が上がるにつれて減少しています。1年生が約31%、2年生が約28%、3年生が約21%と、低学年での利用が中心となっていることがわかります。4年生以降は大きく減少し、4年生で約11%、5年生で約6%、6年生では約3%でした。
学童保育の利用期間を決める際は、各家庭の状況や子どもの希望、学習面での必要性などを総合的に考慮することが重要です。また、自治体によって入所説明会の時期や受け入れ条件が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
参考:放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況|厚生労働省
4-3.共働きでも放課後に習い事をさせられる?
仕事と育児を両立するなかで、子どもに習い事をさせるかは、多くの保護者が直面する課題でしょう。
共働き世帯の習い事における最大の課題は、送迎の時間確保です。平日の決まった時間に送迎することが難しく、子どもの習い事を諦めてしまう家庭も少なくありません。
しかし、民間の学童保育施設では、英語や運動、ダンスなどの専門的な教育プログラムが組み込まれているケースがあります。なかには日常会話を英語で行う施設もあり、習い事と学童保育を効率的に組み合わせることが可能です。
学童保育と習い事が一体となったサービスは、共働き家庭にとって強い味方です。施設ごとに提供内容が異なるため、事前に見学や問い合わせをして、子どもに合った環境を選びましょう。
5.小学生の成長を支える放課後の過ごし方を考えよう

小学生の放課後の過ごし方は、子どもの成長や家庭環境によって大きく異なります。学童保育、習い事、友達との遊び、自宅での留守番など、それぞれの選択肢にはメリットがあり、親としてはバランスを意識しながら適切な方法を選ぶことが重要です。学年ごとに変化する子どものニーズに対応しつつ、安全で充実した時間を提供することが、健全な成長につながります。
一方、共働き家庭では、放課後の過ごし方の選択肢が限られることがあります。そのような場合は、習い事と一体型の学童保育を選ぶことで、放課後の時間をより有意義にできるでしょう。なかでも特に注目なのが、英語で預かる学童保育「Kids Duo(キッズデュオ)」です。
Kids Duo(キッズデュオ)では、英語環境を通じて自然に英語が身につき、子どもたちは楽しみながら学ぶことが可能です。遊びと学びを両立させる多彩なプログラムや、年齢を超えた集団活動を通じて、国際的な感覚や高いコミュニケーション力も育まれます。送迎サービスや最長20時までの延長預かりにも対応しており、共働き世帯でも安心してご利用いただけます。
Kids Duo(キッズデュオ)では無料体験を実施しており、お近くのスクールでその魅力を体感できます。ぜひ一度、実際のプログラムを体験し、安全で充実した環境のなかで才能を伸ばし、将来の成長につながる放課後の過ごし方を一緒に考えていきましょう。
執筆者:英語で預かる学童保育Kids Duo
コラム編集部