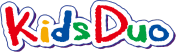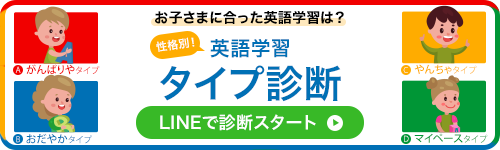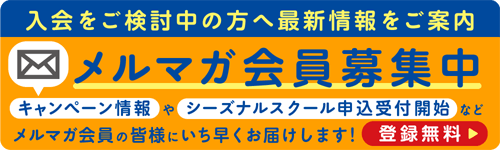「放課後や夏休みの過ごし方に不安がある」「学童と習い事を両立させる方法がわからない」と悩む共働き家庭の方は多いでしょう。
共働きでも、学童保育や習い事、各種支援サービスを組み合わせることで、子どもが安心して過ごせる環境を確保できます。また、施設内で習い事ができる学童を選べば、移動の負担を減らしながら、子どもの成長をサポートすることも可能です。
本記事では、小学生のいる共働き家庭が直面する7つの課題と、それを解決する8つの具体的な対策を紹介します。さらに、学童と習い事を両立する方法や、学童内で習い事を提供しているサービスなども詳しく解説します。
共働き家庭特有の悩みに対する具体的な解決策がわかり、子育てと仕事の両立に向けた実践的なヒントを得られるでしょう。子どもが安心して成長できる環境を整えたい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
1.共働きは小学生がいる家庭でも続けられる?

厚生労働省の統計によると、共働き世帯は年々増加しており、小学生の子どもを育てる家庭でも多くの保護者が仕事と育児を両立しています。令和4年度の東京都の調査では、都内の小学生までの子どもを育てる世帯の66.7%が共働きであり、前回調査(平成29年度)より5.2ポイント増加しました。
共働きを続ける家庭は、子どもの放課後の過ごし方や学校行事への参加など、さまざまな不安を抱えているでしょう。しかし近年では、学童保育やファミリーサポートなどの支援の選択肢が増え、共働き家庭が仕事と育児を両立しやすい環境が整いつつあります。
また、共働き世帯が増えている現状を踏まえると、小学生がいる家庭でも適切な工夫をすれば仕事と家庭の両立は十分に可能だといえます。
参考:共働き等世帯数の年次推移|厚生労働省
参考:東京の子供と家庭 令和4年度福祉保健基礎調査 調査結果の概要|東京都
2.共働きで小学生がいる家庭の7つの課題

小学生の子どもがいる共働き家庭では、仕事と育児を両立するためにさまざまな課題に直面します。特に、放課後の過ごし方や長期休暇の対応、学校行事への参加、学習サポートなど、日々の生活のなかで解決しなければならない問題は多くあるでしょう。
ここでは、共働き家庭が抱える7つの課題を詳しく解説します。
2-1.放課後の過ごし方
共働き家庭にとって、子どもが放課後に安全に過ごせる居場所を確保することは重要な課題です。放課後に子どもが一人で過ごす時間が長くなれば、子どもの安全や健全な育成に影響を及ぼす可能性があります。
特に小学校低学年の場合は授業の終了時間が早いため、放課後の居場所作りに苦労する家庭も少なくありません。学童保育を利用する方法もありますが、地域によっては定員がいっぱいで希望通りに利用できないこともあるでしょう。
また、公立の学童保育施設は18時頃までしか開いていないところも多く、フルタイム勤務の保護者は迎えの時間に間に合わないことも問題の一つです。仕事の終業時刻を学童保育の終了時刻に合わせる必要があり、職場での時間管理に苦労する保護者もいるでしょう。
2-2.夏休みなどの長期休暇の過ごし方
夏休みや冬休みなどの長期休暇も、共働き家庭にとって大きな課題となります。学校がある期間とは異なり、一日中子どもが一人で過ごす時間が発生することで、安全面や生活習慣の乱れが懸念されるためです。
学童保育を利用すれば、子どもが安全に過ごせる環境を確保できますが、お弁当の準備など長期休暇特有の負担もあります。朝の時間が忙しい共働き家庭にとって、お弁当を作る時間の確保は大きな負担となるでしょう。
また、夏休みの宿題を一緒に取り組む時間や、思い出作りの機会を設けるのが難しくなることも悩みの一つです。保護者が仕事で忙しいと、子どもが宿題を後回しにしてしまったり、自由研究などを十分にサポートできなかったりすることもあります。
2-3.学校行事やPTA活動への参加
共働き家庭では、学校行事やPTA活動への参加が難しいという問題もあります。授業参観や運動会、保護者会などのイベントは平日に開催されることが多く、参加するには仕事の調整が欠かせません。
また、授業参観後に保護者向けの懇談会が行われることもあります。懇談会まで参加するとなると、学校での滞在時間が長くなるため半日休暇では足りず、一日有給を取得しなければならないケースもあるでしょう。
さらに、PTAの役員になると、定期的な会議や運営の手伝いが求められます。なかには平日の日中に活動が集中する役割もあり、共働き家庭の保護者は仕事との両立が大きな課題となります。
2-4.宿題や学習のサポート
小学校生活では、子どもの宿題や学習の日常的なサポートが欠かせません。特に低学年のうちは、宿題の進め方やわからない部分のフォローが必要になるため、忙しい保護者にとっては負担が大きくなりがちです。
また、教科書や学習道具の準備確認、翌日の持ち物リストの点検など、細かな配慮も必要です。自主性を育むために子どもに任せたい部分もありますが、重要な連絡事項の見落としや忘れ物は、学校生活に支障をきたす可能性があるので注意しましょう。
加えて、音読の確認や宿題の丸つけなど、保護者の関与が必要な課題もあります。しかし、仕事で疲れて帰宅した後、子どもの学習サポートに十分な時間をとることは容易ではありません。
2-5.子どものトラブルへの対応
学校や友人関係で起こるトラブルにすぐに対応できないことも、共働き家庭の課題の一つです。けんかやケガなどのトラブルが発生すると、学校から緊急の連絡があることも考えられますが、日中に仕事をしながら対応するのは難しい場合も多いでしょう。
また、保育園と比べて、小学校では先生との直接的なコミュニケーションの機会が減少するため、子どもからの説明だけでは事態を正確に把握できないケースもあります。学校での出来事を子どもが親にすべて話してくれるとは限らず、家庭ではトラブルの詳細を把握しにくいという問題もあります。
そのため、トラブルの発生を他の保護者からの連絡で初めて知り、驚くことも少なくありません。
2-6.生活リズムの管理
小学生になると、生活リズムが大きく変わり、共働き家庭ではその調整が難しくなることがあります。
保育園では、午前9時頃までの登園が一般的です。しかし、小学校に進学すると集団登校の時間が決められており、地域によっては午前7時過ぎに家を出発しなければならないケースもあります。
一方で、共働き家庭では仕事から帰宅するのが遅くなり、夕食の時間が20時以降になってしまうことも珍しくないでしょう。その結果、子どもの就寝時間が遅くなり、翌朝の寝覚めが悪くなるという悪循環が生まれてしまいます。
2-7.体調不良や学級閉鎖時の対応
小学校では、突然の体調不良や気象警報による臨時休校、インフルエンザなどの感染症による学級閉鎖といった突発的な休みが発生することがあります。
こうした事態が起きると、共働き家庭ではどちらかが仕事を休まなければならず、仕事のスケジュール調整が必要となります。特に、繁忙期や重要な会議がある日に子どもが体調を崩すと、休みを取りにくい状況になり、対応に困るケースもあるでしょう。
また、インフルエンザなどの感染症で学級閉鎖になると、数日間にわたって学校に通えなくなることも。このような場合、学童保育も利用できなくなるため、子どもをどこで過ごさせるかが大きな問題になります。
3.共働きだとどうしてる?小学生がいる家庭の工夫8選

共働き家庭では、小学生の子どもが安全で充実した日々を送れるように、さまざまな工夫が求められます。仕事と育児の両立には、保育施設や家族のサポートを活用しながら、子どもの成長に適した環境を整えることが大切です。
ここでは、共働き家庭が実践しやすい8つの工夫を紹介します。
3-1.学童保育を利用する
学童保育は、小学生の放課後の居場所として、18時頃まで子どもを預かる施設です。学童保育を利用すれば、保護者が仕事をしている間も、子どもは決まった場所で友達と過ごしながら、宿題や遊びの時間を確保できます。しかし、自治体によっては定員が限られており、希望者全員が入れないこともあるため注意しましょう。
学童保育施設は多くの場合、夏休み期間中も利用可能です。夏休み限定の受け入れをしている施設もあり、8時頃から18時頃までの預かりに対応しているケースが一般的です。
夏休み中も基本的に活動内容は通常期間と同様ですが、季節限定のイベントやプール活動などの特別プログラムが提供されることもあります。
3-2.習い事をする
習い事を取り入れることは、子どもが放課後を有意義に過ごせるだけでなく、新しいスキルを身につける機会にもなります。また、週に1回でも好きな習い事に通うことで、気分転換にもなり、モチベーションの向上につながるでしょう。
たとえば、スポーツ系の習い事では体力をつけると同時に、チームワークや礼儀を学べます。音楽や美術などの芸術系の習い事では、創造力を育んだり、子どもの個性を伸ばしたりすることが可能です。
最近では、送迎付きのスクールやオンラインで受講できる習い事も増えており、保護者が忙しくても無理なく習い事を続けられる環境が整っています。どんな習い事が子どもに合っているのかを見極めながら、家庭の負担になりすぎない範囲で取り入れましょう。
3-3.サマースクールに参加する
夏休みが6週間から3か月に及ぶ海外では、子どもの学習機会や交流の場としてサマースクールが広く普及しています。日本国内でも、語学学校による英語サマースクールや、全寮制学校による短期留学プログラムが提供されています。
サマースクールでは、ネイティブ講師による指導のもと、幼児や小学生でも安心して英語学習や異文化体験に取り組むことが可能です。国際感覚を養う貴重な機会として、近年注目を集めています。
海外のサマースクールでは、2か月にわたる長期コースも用意されています。一方で国内プログラムの場合、開催期間は7月から8月の夏休み期間中で、1週間程度が一般的です。長期で参加するのが難しい場合でも、短期間のプログラムに参加することで、夏休みの過ごし方にメリハリをつけられるでしょう。
3-4.ファミリーサポートを活用する
ファミリーサポートセンターは、地域における子育て支援の相互援助システムです。市区町村または委託を受けた団体が運営するため、安心して利用できます。
主なサービス内容は、子どもの一時預かりと送迎支援です。学童保育の前後の時間帯や長期休暇中の預かり、保護者の急用時の対応などに対応します。また、保育所や習い事への送迎サービスも提供しています。
ファミリーサポートは、仕事と育児の両立支援を目的として、当時の労働省により創設されました。現在では、すべての子育て家庭が利用できる支援制度として定着しており、地域の支援会員による柔軟できめ細かなサポートを受けられる点が大きなメリットです。
3-5.祖父母や親戚の協力を得る
両親や祖父母が近くに住んでいる場合、放課後の見守りや学童保育の送迎など、日常的な支援を得られる可能性があります。祖父母に頼ることで、子どもが家族とのつながりを深められるというメリットもあるでしょう。
また、学級閉鎖や臨時休校など、急な対応が必要な場合にも祖父母の支援は心強い味方です。仕事を休むのが難しいときでも、祖父母に預かってもらうことで、安心して仕事を続けられます。
加えて、宿題の確認や持ち物の準備など、学習面をサポートしてもらうことも可能です。ただし、無理に頼りすぎると負担をかけてしまうため、事前に相談して適度な範囲で協力を得るようにしましょう。
3-6.家事代行サービスを利用する
仕事と子育てを両立するためには、家事の負担を減らすことも大切です。掃除や食事の準備、洗濯などを家事代行サービスに依頼することで、家庭内の負担を軽減できます。
家事代行サービスを利用すれば、家事の心配をせずに仕事に集中できるため、業務効率が向上します。さらに、家族との時間や自分自身の趣味の時間を確保しやすくなり、心のゆとりも生まれるでしょう。
近年、家事代行サービスは子育て世帯向けのサービスも充実しています。習い事への送迎や留守中の見守り、食事の準備など、子どもの生活全般をサポートするメニューも用意されています。各家庭のニーズに合わせて、必要なサービスを選択するとよいでしょう。
3-7.GPS機能付き携帯を持たせる
子どもの安全管理のために、GPS機能付きの携帯を持たせるのもおすすめです。子どもの帰宅や安全の確認が簡単にできるため、保護者も安心感を得られます。
小学校への携帯電話の持ち込みが禁止されている場合でも、自宅に置いておくことで放課後の連絡手段として活用できます。帰宅時の連絡習慣をつけることで、子どもの生活リズムを把握しやすくなるでしょう。また、GPS機能を搭載した携帯なら、習い事への移動経路の確認も可能です。
ただし、携帯の使い方にはきちんとルールを設けましょう。どのような機能が必要かを考え、ニーズに合った機種を選ぶことが大切です。
3-8.働き方を見直す
子どもの小学校入学を機に、働き方の変更を検討する保護者も増えています。フルタイム勤務から時短勤務やパートタイムへの移行、職場内での配置転換なども、仕事と子育てを両立するための選択肢の一つです。
勤務形態の変更が難しい場合は、フレックスタイム制度やリモートワークを利用することで、子どもとの時間を確保しやすくなります。企業によっては育児支援制度が充実している場合もあるため、どのような制度があるか確認し、利用を検討してみるとよいでしょう。
環境の変化を不安に感じることもありますが、子どもが新しい環境に挑戦する時期だからこそ、保護者も前向きな気持ちで自分に合った働き方を選びましょう。
4.共働き家庭の学童&習い事の両立はできる?

学童保育施設の方針や支援内容によっては、子どもの習い事との両立を実現できます。
学童保育中の習い事参加には、「中抜け」という仕組みが関係します。これは学童保育の時間内に一時的に外出し、習い事に参加した後で学童保育に戻ることです。施設によって中抜けの可否は異なるため、事前に確認しておきましょう。
近年は、習い事のプログラムを組み込んだ民間学童保育施設も増加しています。英会話やプログラミング、音楽など、多彩な学習機会を提供しているところもあるので、ぜひチェックしてみてください。
また、一部の学童保育施設では、習い事への送迎サービスも実施しています。複数のスタッフによる安全な送迎体制を整えており、保護者の負担軽減にもつながっています。
5.共働き家庭の小学生が楽しく成長できる環境を作ろう

共働き家庭における小学生の子育ては、放課後の過ごし方や長期休暇の対応など、さまざまな課題に直面します。しかし、学童保育や習い事、ファミリーサポートなど、複数の支援制度やサービスを組み合わせることで、これらの課題を解決することが可能です。
最近では、学童保育と習い事が一体となった施設も増えており、共働き家庭にとって利便性が高まっています。このような施設では、学童保育の時間内に英語、プログラミング、スポーツなどの習い事を受講できるため、送迎の負担を減らしながら、子どもの成長をサポートできるでしょう。
特に、英語環境で過ごせる学童保育「Kids Duo(キッズデュオ)」なら、預かり時間を活用して英語に触れながら自然に言語を習得できます。
送迎サービスや延長預かり、セーフティメールなど、充実したサポート体制も整っており、保護者が安心して仕事に集中できる環境が整備されています。また、単なる学童保育ではなく、社会性やコミュニケーション力など将来に役立つスキルを伸ばせるのも大きな魅力です。
Kids Duo(キッズデュオ)では無料体験を実施しており、実際の環境やプログラムを体験できます。「どのような雰囲気なのか?」「子どもが楽しめるのか?」といった不安を解消するためにも、ぜひご参加ください。
執筆者:英語で預かる学童保育Kids Duo
コラム編集部