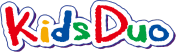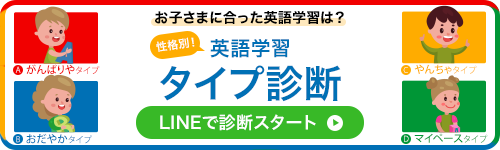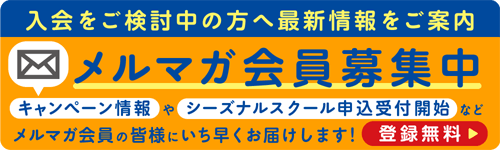「共働き世帯なのに学童に落ちてしまった」
「学童に入れないことがわかり、今後何をすべきかわからなくなった」
「学童に落ちてしまったが、子どもを一人で留守番させるのは怖い」
学童の選考結果が届き、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。学童に落ちた・学童に入れないときの対処法は、子どもの学年によって変わります。子どもが現在できることに合わせて、環境を整える必要があるからです。
この記事では、学童の基本情報や「学童に落ちた、入れない」際の影響などを説明したうえで、具体的な対処法を解説していきます。学童に関する悩みを解決したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
1.「落ちた、入れない」の前に!学童の基本情報

「学童に落ちた、入れない」という悩みの対処法を見ていく前に、まずは学童の基本的な情報をおさらいしておきましょう。正しい情報を知っておくことで、より的確な行動がとれるようになります。
ここでは、「学童はそもそもどんな施設なのか」「学童にはどんな種類があるのか」「学童ではどんなプログラムを経験できるのか」という3つの視点で説明していきます。
1-1.放課後や長期休暇に児童を預けられる施設のこと
学童とは、仕事をはじめとした事情によって保護者が自宅にいない児童を一定期間預けられる施設、サービスのことを指します。共働きの場合、放課後や長期休みに児童をどこに預けるかといった問題が起こることがあります。そのため、学童のような施設・サービスが重要視されているのです。
なお、学童は現在こども家庭庁が管轄している「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」の一種です。名称は正確に定義されていないため、「学童クラブ」「学童保育」などの言葉で呼ばれているケースも少なくありません。
名称は地域によって変わることがあるので、自分の地域がどんな呼び方をしているのか確認しておきましょう。
参考:放課後児童健全育成事業について|こども家庭庁
1-2.種類は公立・民間の2つ
学童は、公立の施設と民間の施設の2種類に分かれます。公立は地方自治体が運営していますが、民間は民間企業やNPO法人などが運営しているところが大きな違いです。
公立と民間には、下記のように他にもさまざまな違いが存在します。
| 学童の種類 | 料金 | サービス内容 | 応募条件 |
|---|---|---|---|
| 公立 | 安め | 民間よりは独自のプログラムが充実していない傾向にある | 民間よりは厳しめ |
| 民間 | 高め | 公立よりはプログラムが充実している傾向にある | 公立よりは緩め ※人気施設の場合は選考に通過できないケースもある |
ちなみに、施設によっては公立と民間を併用することも可能です。それぞれのよい部分と悪い部分を理解し、自分の家庭に合った選択をしましょう。
1-3.勉強やスポーツなどプログラムはさまざま
学童では、施設が用意したプログラムによって子どもたちが多種多様な経験ができます。主な例は以下のとおりです。
- 学校の宿題をはじめとした学習補助
- 友だちとの遊び
- 読書
- おやつ
- スポーツ
- 英語
- プログラミング
- ダンス
このようなプログラムは、利用する施設によって内容が大きく変わります。特に民間の施設は、一般的な宿題や遊び以外のバラエティ豊富なプログラムが多くなる傾向にあるでしょう。
そのため、各施設のプログラム内容を整理し、より自分の希望にマッチした施設を選ぶ必要があります。
2.「学童に落ちた、入れない」理由とは?

次に、なぜ「学童に落ちた」「学童に入れない」といった状況に陥ってしまうのか、その理由を解説します。
2-1.全体的な需要の増加
まず、学童そのものの需要が全体的に高まっていることが大きな理由です。最近は共働き世帯が増えているため、子どもの帰宅時に保護者がいない家庭も少なくありません。
ここで、「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」の2023年のデータを見てみましょう。共働き世帯が1,278万世帯(※)であるのに対し、専業主婦世帯は517万世帯(※)であることからも、その傾向が伺えます。
※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構|共働き等世帯の状況 ―労働力調査(詳細集計)結果から―
ちなみに、子どもが多い地域や人口そのものが密集しているエリアでは、学童の需要もさらに高いと予想できます。自分が居住している地域が上記に該当する場合は、より迅速な対処が必須になるでしょう。
2-2.施設の不足
学童の需要が増している状況に対して、関連施設が不足していることも理由の一つです。
こども家庭庁の2024年のデータによると、学童をはじめとした放課後児童健全育成事業を利用できなかった待機児童は全体で17,686人(※)となっています。
※出典:こども家庭庁|令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況
このようなデータからも、学童施設が不足していると考えられます。今後施設が増加したとしても、学童に入りにくい現状がすぐに改善されるわけではありません。よって、学童以外の選択肢に目を向けてみることも大切でしょう。
3.「学童に落ちた、入れない」とどうなるのか?

続いて、「学童に落ちた、入れない」状態になると、子どもや家庭にどのような影響が出るのか見ていきましょう。これらを把握することで、学童やそれに準じた施設、サービスを取り入れる重要性が理解できます。
3-1.家族の仕事に悪影響が出る
子どもが学童に入れないと、家族が仕事をやめなければならない・時短勤務に切り替えることで収入が低下するなどの可能性が高まります。学童のかわりに家で時間を過ごさなければならない子どもを世話する必要があるからです。早退が増えることで、業務をカバーしてくれる同僚などへの対応も求められるでしょう。年から高学年にかけては、遊びたい気持ちが強くなり、家庭での学習がおろそかになるケースも増えます。
族の仕事に悪影響が出ると、家庭全体の雰囲気悪化やストレスの増加にもつながります。健康的かつ明るい家庭を築くためには、学童やそれに準じた施設、サービスを効果的に利用することが重要です。
3-2.子どもを危険にさらすリスクがある
子どもが学童などに入らない場合、交通事故や傷害事件などの思わぬアクシデントに巻き込まれるリスクがあります。大人の目が届かない時間帯が増えることによって、予想外のトラブルが勃発する可能性があるからです。
また、仕事中に「子どもが事件に巻き込まれているかもしれない」などと考えると、保護者の精神的負担も大きくなってしまいます。親がストレスを抱えることで、結果的に子どものメンタル不調にもつながる可能性があるので、こういった状況はなるべく避けたほうがよいでしょう。
4.【学年別】「学童に落ちた、入れない」ときの対処法

もし学童に落ちてしまっても、子どもの学年に合わせた適切な対処法を実施することで、子どもの成長を手助けしやすくなります。ここでは、新1年生・2~3年生・4~6年生と3つの年齢層に分けて、おすすめの対処法を紹介していきます。
4-1.新1年生で学童に落ちた場合
新1年生の場合、まず実施すべき対策は「自分のエリア内でまだ応募可能な学童をリストアップし、選考に参加すること」です。小学校入学時は比較的学童に落ちにくいタイミングなので、第一志望の学童に入れなくても、他の学童なら選考に通るかもしれません。
もし公立の学童に落ちてしまったのなら、民間の施設まで視野を広げてみるのもおすすめです。公立よりも民間のほうが選考基準が緩いといわれているため、通る可能性があります。
また、民間の学童施設は、公立では体験できないようなプログラムが多く用意されているところもポイントです。たとえば、以下が例に挙げられます。
- 芸術に触れる活動
- 理科の実験
- 工作、絵画、工芸
- 野外アクティビティ
- AI(人工知能)の勉強
小学1年生の頃から幅広い経験を積むことで、興味を持つ分野が増えたり、自分の可能性を広げたりできるでしょう。新1年生以外のケースでも、ぜひ民間の学童を選択肢として検討してみてください。
4-2.2~3年生で学童に落ちた場合
小学校2~3年生は、習い事を始める・増やすことで保護者がいない時間をカバーしましょう。2~3年生になると、入学したばかりの新1年生と比べると社交性が身についてくるため、新しい環境下の友人や大人たちとも、人間関係を構築しやすくなるでしょう。
具体的な習い事の例は、下記をチェックしてみてください。
- 学習塾
- スイミング教室
- スポーツクラブ
- ダンスレッスン
- 英会話教室
- ピアノ教室
- 書道教室
このなかでも、送迎サービス付きの習い事を選ぶと家族の負担を軽減できます。子どもの送迎のために、仕事を早めに切り上げる必要がなくなるからです。これは、共働き世帯にとって大きなポイントとなるでしょう。
また、子どもが一人で帰宅するよりも安全性が高く、その間に仕事をしている両親の精神的ストレスを減らせるという面もあります。
4-3.4~6年生で学童に落ちた場合
小学校4~6年生の場合は新しく入れる学童を探すよりも、子どもに留守番を覚えてもらうことで問題を解決しましょう。高学年になると学童の選考そのものに落ちやすくなるため、学童以外の選択肢を検討したほうが効率的です。子どもに自信をつけるよい機会でもあるので、安全性に配慮しながら留守番を覚えてもらいましょう。
留守番を覚えてもらうにあたって重要なのは、「予想外の出来事への対応策を教えておくこと」です。たとえば、下記などが例に挙げられます。
- 突然の来客・電話への対応
- 地震をはじめとした自然災害への対応
口頭で教えるだけでなく、内容をマニュアル化しておくことで、保護者がいない状態でも子どもが冷静に対応できるようになるでしょう。
また、帰宅中に不審者から目をつけられないよう、わかりにくい場所に家の鍵を保管しておくことも大切です。具体的には、ランドセルの中に入れたポーチなどが例に挙げられます。
5.【共通】「学童に落ちた、入れない」ときの対処法4選

最後に、子どもがどの学年であっても活用しやすい対処法として、代表的なものを4つ紹介します。それぞれメリットや特徴があり、複数の方法を同時に取り入れることも可能なので、自分の状況と照らし合わせてより適切な方法を選びましょう。
5-1.児童館を利用する
児童館を利用することで、学童に落ちてしまった状況をカバーできます。児童館は学童よりも自由に使用しやすい施設であるうえに、料金がかからないケースも多いからです。
児童館とは、18歳未満の子どもたちを対象にした児童福祉施設のことです。学童に近い施設だと感じるかもしれませんが、児童館は学童と異なり「子どもたちが遊べる場をつくる」ことを目的としています。学童のように、保護者が家にいない子どもを預けるための施設ではありません。
その分、施設内では子どもが自由に遊べるというメリットがあります。自由度の高い施設で、子どもにのびのびと時間を過ごしてほしいなら、児童館がおすすめです。
5-2.ベビーシッターを頼む
ベビーシッターに子どもの世話を依頼するのも、学童の代替案として有効です。多くのベビーシッターは、小学校までの子どもに対応しています。送迎や自宅での留守番はもちろん、料理や掃除などの家事まで依頼できることもあります。
また、土日や夜間、長期休暇などに対応しやすいところもベビーシッターの魅力です。日程や時間帯を自由に設定できるケースも多いので、両親の勤務時間が不規則な場合はベビーシッターの利用が適しているでしょう。
5-3.ファミリーサポート制度を活用する
ファミリーサポート制度の利用も、代表的な方法の一つです。ファミリーサポートを使うことで、保護者がいない時間帯の送迎や預かりを第三者に依頼できます。
そもそもファミリーサポート制度とは、地方自治体などが運営する育児サポートのことです。サポートを受けたい人とサポートしたい人をつなぐマッチングサービスでもあります。
ただし、サポート側の人数が不足していることから、家族のスケジュールに合わせて自由に依頼することは難しいといわれています。スポット的な利用や短時間の預かりでも問題ない場合におすすめできるでしょう。値段が比較的リーズナブルなところもポイントです。
5-4.家族や友人にサポートしてもらう
これまでに紹介した制度やサービスが使えない状況なら、家族や友人にサポートしてもらうのも一つの方法です。もし両親の実家や信頼できる友人が近くに居住している場合は、送迎や預かりを依頼してみてはいかがでしょうか。
なお、依頼にあたって相手にお礼をすることを忘れないようにしましょう。今後の人間関係を良好に保つためにも、感謝をしっかりと伝えることが大切です。
6.「学童に落ちた、入れない」場合は自分に合った対処法を実施しよう

この記事では、「学童に落ちてしまった」「学童に入れない」場合の対処法について詳しく解説しました。適切な対処法は子どもの年齢層によって変わってくるうえに、現在利用できる制度やサービスにもそれぞれ特徴があります。そのため、自分の家庭に適した対処法を厳選することが必要です。
そのなかでも民間学童は「多様なプログラムが経験できる」などの特徴があるため、学童保育で悩んでいる方はぜひ利用しましょう。
「Kids Duo(キッズデュオ)」なら、英語に特化したプログラムで子どもたちの可能性を高めることが可能です。英語のみを使うプロフェッショナルな環境に身を置くことで、子どもたちは今後の成長に役立つスキルを身につけられるでしょう。
また、送迎用バスのサービスを完備しており、長期休暇の対応も時期によっては可能です。「学童に落ちた、入れない」とお悩みの方は、「Kids Duo(キッズデュオ)」の利用をぜひ検討してみてくださいね。
執筆者:英語で預かる学童保育Kids Duo
コラム編集部