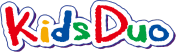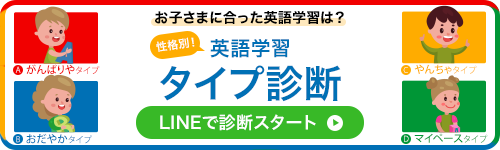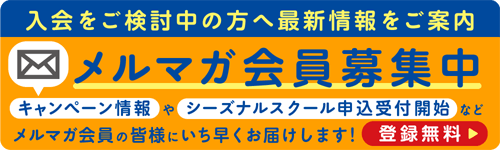「学童保育の料金はどれくらいかかるの?」「公立と民間の学童の違いは?」と疑問に思っている方も多いでしょう。
学童保育の料金は、公立と民間で異なります。また、自治体による助成制度を活用すれば、負担を軽減できる可能性もあります。
本記事では、学童保育の料金の仕組みや公立・民間学童の違い、学童選びのチェックポイントについて解説します。学童保育の料金や特徴を正しく理解することで、家庭に合った最適な学童を選べるでしょう。お子さまにぴったりの学童保育を見つけるためにも、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
1.学童保育の基礎知識

学童保育には、公立学童保育(放課後児童クラブ)、民間学童保育、放課後子ども教室の3種類があり、それぞれ運営形態や料金、利用条件が異なります。
ここでは、それぞれの学童保育の利用条件や料金の違いを解説します。
1-1.学童保育とは?預けるための条件
学童保育とは、保護者が仕事やその他の事情で昼間に家庭にいない小学生を対象に、放課後や長期休暇中に安全な居場所を提供するサービスです。公立学童保育(放課後児童クラブ)、民間学童保育、放課後子ども教室の3つの種類があり、それぞれ入所条件が異なります。
公立学童保育(放課後児童クラブ)
- 小学1年生から6年生が対象(自治体によって異なる)
- 保護者がフルタイムまたはパートタイムで働いていることが条件
- 申し込みは主に自治体を通して行う
- 定員が決まっており、申し込み多数の場合は選考がある
民間学童保育
- 施設ごとに対象年齢や入所条件が異なる
- 保護者の就労要件がない場合もある
- 直接施設に申し込み、定員が空いていれば入所可能
放課後子ども教室
- 地域の公立小学校に通う子どもなら誰でも参加できる
- 学童保育と異なり、保護者の就労要件はなし
学童保育を利用する際は、各施設の特徴や条件を理解し、家庭の状況に合った選択をしましょう。
1-2.料金は学童保育の種類で違う?
学童保育の料金は、施設の種類によって異なります。公立学童保育(放課後児童クラブ)は自治体が運営しているため、比較的低額で利用できます。一方で、民間学童保育は運営費用を保護者が負担するため、設定料金は高めです。
公立学童保育の料金は、自治体によっては所得に応じた減免制度があります。また、おやつ代や教材費などが別途必要になるケースもあります。
民間学童保育の料金は、施設によって異なりますが、公立と比べると高額になるのが一般的です。基本料金に加え、送迎サービスや習い事などのオプションを追加すると、さらに費用がかかることもあるでしょう。
放課後子ども教室は、自治体や地域団体が運営しているため、無料または低額で利用できるのが特徴です。費用を抑えながら子どもが安全に過ごせる環境を提供している点が大きなメリットといえます。
2.【種類別】学童保育の特色と料金相場

子育て世帯のニーズに合わせて、学童保育のサービス内容も多様化しています。各施設の特色と料金体系を理解することで、それぞれの家庭に合わせた選択が可能です。
運営形態によって、提供されるサービスの内容や質、そして料金設定には違いがあるため、以下の表を参考に比較検討するとよいでしょう。
| 学童保育の種類 | 運営主体 | 料金の目安 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 公立学童保育 (放課後児童クラブ) |
自治体 | 月額4,000~10,000円程度 |
|
| 民間学童保育 | 民間企業 | 月額30,000~70,000円程度 |
|
| 放課後子ども教室 | 自治体など | 無料〜数千円程度 |
|
2-1.公立学童保育(放課後児童クラブ)
公立学童保育(放課後児童クラブ)は、厚生労働省の管轄下で各地方自治体が運営する公的支援サービスです。
施設の開所時間は場所によって異なりますが、平日の下校時間である12時から14時の間に開所する施設が全体の6割を占めています。終了時刻は18時以降となる施設が多く、一部の施設では19時までの延長保育にも対応しています。
施設の設置場所はさまざまで、小学校内の専用スペースや児童館での運営が一般的です。その他にも、児童センター内での運営や、独立した専用施設での展開、公民館や保育施設に併設されているケースもあります。
利用料金は自治体によって設定が異なり、月額4,000~10,000円程度です。宿題や自習のためのスペースは確保されていますが、あくまでも子どもたち自身の意思で学習に取り組める環境づくりがなされています。
2-2.民間学童保育
民間学童保育は、教育関連企業やNPO団体、学習塾など、多様な事業者が運営しています。大手教育企業による大規模施設から、地域密着型の小規模施設まで、子どもの興味や性格に合わせて選択できます。
施設の営業時間も柔軟で、20時から21時までの延長保育に対応する施設も存在します。放課後の保育に加えて、学習指導や習い事のプログラムを提供する施設も増えており、豊富な活動メニューから好みのプログラムを選べるのが特徴です。
また、送迎サービスを提供している施設もあるため、共働き家庭にとって利便性が高い選択肢の一つといえるでしょう。民間施設の利用料金は月額30,000~70,000円程度となっており、提供されるサービス内容に応じて料金が設定されています。
2-3.放課後子ども教室
放課後子ども教室は、文部科学省が推進する独自の教育支援事業です。留守家庭への支援ではなく、すべての児童を対象とした学習支援や体験活動を提供しています。
放課後子ども教室は、学校施設の空き教室を活用し、地域のボランティアや元教員、企業経験者などが講師を務めます。保護者の就労状況を問わず、すべての小学生が利用できるのが大きな特徴です。学童保育と連携したサービスを提供する動きも始まっています。
自治体によって異なりますが、利用料金は基本的に無料から数千円程度です。基礎的な学習支援は無料で提供されますが、工作や実験などの特別プログラムでは材料費が必要になることもあるでしょう。
3.学童料金の助成・減免制度の内容

学童保育は、家庭の経済状況に応じた利用料金の軽減制度が設けられているケースもあります。各自治体では、特定の条件を満たす世帯向けに、料金の減額や免除を実施しています。
具体的な支援対象としては、生活保護受給世帯や住民税非課税世帯です。また、一人親世帯向けには、申請手続きを経て助成金を受けられる制度も用意されています。さらに、兄弟姉妹が複数いる場合、2人目以降の学童利用料が減額される地域もあります。
支援制度の詳細は自治体によって異なるため、各自治体の窓口で確認しましょう。学童保育の利用料金は、基本的に家庭の負担となりますが、所得や家庭環境に応じた助成・減免制度を活用することで、費用を抑えて利用できる可能性があります。
4.【公立・民間】それぞれの学童の長所と短所
学童保育には、公立と民間の2種類があり、それぞれに長所と短所があります。ここでは、それぞれの学童の長所と短所を解説します。
4-1.公立学童保育の長所と短所
公立学童保育(放課後児童クラブ)は、自治体が運営しているため経済的な負担が少なく、保護者の安心感がある点が大きなメリットです。多くの場合、小学校内やその近くに設置されており、子どもが移動しやすいのもメリットの一つといえるでしょう。
ただし、自治体ごとに運営方針が異なるため、提供されるサービスには違いがあります。
公立学童保育の長所
- 料金が安く、経済的負担が少ない
- 自治体の管理のもと、一定の基準を満たした指導員が配置されている
- 地域の小学校に併設されていることが多く、移動の負担が少ない
一方で、公立学童保育には以下のようなデメリットもあります。
公立学童保育の短所
- 申し込み多数の場合、選考制となり、必ずしも利用できるとは限らない
- 延長保育や送迎サービスがないため、保護者の勤務時間によっては利用が難しい
- 基本的には生活の場として運営されており、宿題のサポートなどはあるが、専門的な学習指導は行われない
定員制限があるため、希望者が多い地域では入所できないケースもあることが大きな課題です。また、自治体の規則に従って運営されるため、柔軟な対応が難しい場合もあります。
4-2.民間学童保育の長所と短所

民間学童保育は、企業やNPO法人が運営しており、サービスの柔軟性が高い特徴があります。公立学童と異なり、保護者の就労条件に関わらず利用できる施設が多く、送迎サービスや習い事などのオプションが充実している点もメリットです。
民間学童保育の長所
- 保護者の就労状況に関わらず、定員に余裕があれば利用できる施設が多い
- 送迎サービスや延長保育があり、共働き家庭にとって利便性が高い
- 宿題サポートや学習指導、英語教育、プログラミング学習など、教育面での充実が期待できる
民間学童保育にもデメリットはあります。
民間学童保育の短所
- 月額料金が数万円以上になることが多く、家庭の負担が大きくなる
- 運営主体によって提供されるサービスの質に差があるため、事前に確認が必要
- 学区外にある施設では、同じ学校の友達が少ない可能性がある
最も大きな課題は、費用が高額になりやすい点です。特に、プログラムが充実している施設では、基本料金に加えて追加費用がかかる場合が多く、公立学童と比べると負担になることがあるでしょう。
公立学童保育と民間学童保育には、それぞれ異なる特徴があります。どちらを選ぶかは、家庭のライフスタイルや子どもの教育方針に合わせて、よく検討しましょう。
5.学童選びで失敗しない!5つのチェック項目

学童保育を選ぶ際には、料金や立地だけでなく、子どもにとって安全で快適な環境であるかを慎重に確認しましょう。また、学童の質は施設ごとに大きく異なるため、事前の情報収集と見学を行い、家庭に合った学童を選ぶことが失敗を防ぐポイントです。
ここでは、学童選びで重視すべき5つのチェック項目を紹介します。
5-1.送迎方法
まず、送迎方法を確認することが大切です。共働き家庭では、学童保育の立地や送迎サービスの有無によって、保護者の負担が大きく変わります。
学校から学童までの距離が徒歩圏内なのか、公共交通機関を利用する必要があるのかを考えなければなりません。民間学童のなかには送迎サービスを提供している施設もあるため、必要に応じて確認しましょう。
さらに、悪天候時や交通機関の遅延などのトラブル発生時に、代替の送迎手段があるかどうかも重要なチェックポイントです。
5-2.保育内容
次に、保育内容を確認しましょう。学童によって提供される保育の内容は大きく異なり、ただ預かるだけの施設もあれば、学習支援や習い事を兼ねたプログラムを用意している施設もあります。
宿題のサポートがあれば、自宅での学習負担を軽減できるでしょう。また、英語教育やプログラミング学習などの学習プログラムが充実している施設もあるため、子どもの成長につながる内容かどうかを検討しましょう。
遊びや体験活動の充実度も重要です。外遊びの時間や創作活動の機会が確保されているかを事前にチェックしておくことが大切です。
5-3.指導員や施設の雰囲気
学童を選ぶ際には、指導員や施設の雰囲気も見逃せません。子どもが毎日通う場所だからこそ、指導員の質や施設の環境をしっかり確認しておきましょう。
指導員が保育士資格や学童指導員の資格を持っているか、子どもとの接し方が適切かを見極めることが大切です。加えて、施設が清潔であるか、トイレや食事スペースが衛生的に管理されているかもポイントです。
さらに、子ども同士の関係性にも注目し、いじめやトラブルが起きにくい環境であるか、指導員が適切に見守っているかも確認するようにしましょう。
5-4.安全性
安全性の確保も学童選びでは欠かせない要素です。学童保育は放課後や長期休暇中に子どもが長時間過ごす場所であるため、防犯対策がしっかり整っているかどうかを確認しましょう。
施設へ出入りするときの管理が適切に行われているか、防犯カメラが設置されているかを確認することで、安全な環境かどうか判断できます。また、怪我や体調不良時の対応が明確になっているか、保護者への連絡体制が整っているかも事前に確認しておきましょう。
万が一に備え、災害時の避難ルートや対応マニュアルが整備されているか、定期的に避難訓練が実施されているかも重要なチェックポイントの一つです。
5-5.子どもの意見
最後に、子どもの意見を尊重することも忘れないようにしましょう。学童を利用するのは、保護者ではなく子ども自身です。どれだけ保護者がよいと感じた施設でも、子どもが楽しめない場所では意味がありません。
学童の雰囲気や活動内容が子どもの興味に合っているかを確認し、友達ができそうな環境かどうかを考慮しましょう。すでに知っている友達がいるか、学童の雰囲気が馴染みやすいかを確認するとともに、見学や体験時に子どもが楽しそうにしているか、不安そうにしていないかを観察することが大切です。
6.学童保育の料金でよくある質問

学童保育の利用を検討する際、特に料金に関する疑問を持つ家庭は少なくありません。ここでは、学童保育の料金に関するよくある質問に答えていきます。
6-1.夏休みだけ学童保育に通う場合の料金は?
多くの学童保育は、夏休みのみの利用にも対応しています。しかし、施設の種類や運営方針によって、受け入れ条件や料金体系は大きく異なります。また、定員の関係で夏期限定の利用を制限している施設もあるため、必ず事前に確認しておきましょう。
公立学童保育では、夏休みの間は通常8時頃から18時頃まで利用可能です。利用料金は一般的に、月額7,000~15,000円程度に設定されています。
民間学童保育では、夏休み限定で利用する家庭も多くみられます。しかし、利用料金は公立学童保育の数倍になる場合もあるため、家庭の状況に合わせて選択しましょう。
基本的な生活リズムは通常期間と同様ですが、夏季特別イベントやプール活動など、季節に応じたプログラムが用意されているのが一般的です。施設を選ぶときは、活動内容と料金のバランスを考慮することが大切です。
6-2.学童保育の料金は無償化されないの?
学童保育では、ほとんどの地域で利用料金の支払いが必要です。多くの自治体で、家庭の経済状況に応じた助成・減免制度を設けていますが、現時点で学童保育の完全無償化を実現している自治体は極めて限られています。
財政面での課題が大きく、全国的な無償化の実現にはまだ時間がかかる見通しです。ただし、一部の自治体で無償化を実現している事例があることから、将来的に無償化される可能性は残されているといえるでしょう。
参考:小樽市における子育て支援の取組について(放課後児童クラブ手数料無償化及びこども医療費助成の高校生以下実質無償化)|小樽市こども未来部 放課後児童課 こども福祉課
7.学童保育の料金や特色を比較してベストな選択をしよう

学童保育には、公立学童保育と民間学童保育があり、それぞれに特徴があります。公立学童は自治体が運営しており、料金が安く安心して利用できる点が魅力ですが、定員が限られているため、申し込み多数の場合は利用できないこともあります。
一方、民間学童は送迎サービスや長時間預かり、学習支援などの充実したサービスを提供しているため、共働き家庭にとって利便性が高い選択肢の一つです。費用はかかりますが、子どもの成長を考えると、教育面への投資として検討する価値があるでしょう。
学童保育は単なる「預ける場所」ではなく、子どもの成長を支える環境です。送迎方法や保育内容、指導員の質、安全性、そして子ども自身の意見を考慮しながら、最適な学童を選びましょう。
その選択肢の一つとして、英語環境で過ごせる学童保育「Kids Duo(キッズデュオ)」がおすすめです。Kids Duo(キッズデュオ)は、英語を「勉強する」のではなく「英語に浸る」環境を提供し、長時間にわたって英語を使って過ごすことで、自然に英語を身につけられます。
さらに、音楽や工作、ゲームなど、多彩なプログラムを通じて、子どもたちの社会性や協調性を育むことも特徴の一つです。送迎サービスや延長保育も充実しており、共働き家庭でも安心して利用できます。
Kids Duoでは、実際の学童環境を体験できる無料体験を実施しています。お子さまの未来の可能性を広げる学童環境を、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。
執筆者:英語で預かる学童保育Kids Duo
コラム編集部