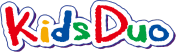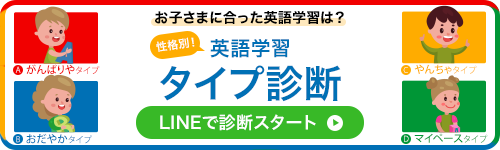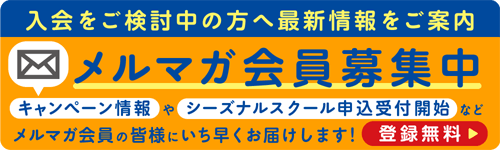「習い事の送迎が大変」「忙しくて子どもが習い事を続けられるか不安」と悩んでいる共働き家庭の方は多いでしょう。
近年、送迎サービスのある教室や学童保育と連携した習い事など、新しいスタイルの選択肢が増えており、共働き家庭でも子どもの習い事を無理なく継続できます。
本記事では、共働き家庭が習い事を続ける際に直面する課題や、その解決策を詳しく解説します。共働きでも無理なく習い事を続ける方法がわかり、子どもに合った学びの環境を整えるヒントが得られるので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
1.共働きだと習い事ができない5つの問題

共働きの場合、子どもに習い事をさせたくても、時間や労力の面でさまざまな問題に直面することもあるでしょう。特に、送迎や付き添い、家庭内のスケジュール管理などが大きな負担となり、結果的に習い事を諦めてしまうケースも少なくありません。
ここでは、共働き家庭が習い事を続けるうえで直面しやすい5つの問題を詳しく解説します。
1-1.送迎時間を確保できない
子どもの習い事の送迎問題は、共働き家庭の大きな悩みの一つです。仕事が長引いたり、通勤に時間がかかったりすると、習い事の開始時間に間に合わないこともあるでしょう。
特に平日の夕方の習い事は、勤務時間と重なることが多いため、送迎に頭を悩ませる家庭も多いかもしれません。
また、兄弟姉妹がいる場合、それぞれが違う習い事をしていると、送り迎えのスケジュール調整がさらに困難になることもあります。子どもの安全を確保しつつ、無理なく通わせる手段を見つけることが大切です。
1-2.当番や付き添いが負担になる
なかには、保護者が送迎だけでなく、当番や付き添いを求められるケースもあります。特にスポーツ系の習い事では、練習の際に保護者が当番制でサポートをするのが一般的です。
また、低学年の子どもが参加する習い事では、見守りや着替えの補助など、保護者が不可欠なものもあります。このような場合、共働き家庭では仕事と家庭のスケジュール調整が必要です。平日だけでなく、週末に時間を割く必要のある習い事もあるでしょう。
仕事の都合で当番をこなせないと、周囲に迷惑をかけてしまうのではないかと気を遣い、精神的な負担につながることも考えられます。
1-3.宿題をする時間がない
子どもが習い事をすることで、宿題の時間を確保しにくくなることも共働き家庭でよくある悩みです。特に低学年の子どもは、保護者のサポートが不可欠です。わからない問題でつまずいたまま放置すると、勉強嫌いになってしまうリスクもあるでしょう。
また、平日の夕方に習い事がある場合、帰宅後すぐに夕食や入浴の時間になり、宿題に取り組む余裕がなくなることも考えられます。宿題が後回しになると寝る時間が遅くなり、生活リズムが乱れる原因にもなります。
運動系の習い事では、疲れてしまって宿題に集中できないかもしれません。
1-4.お弁当の準備が大変
習い事の内容によっては、夕方以降の時間帯に活動があり、お弁当の準備が必要になることがあります。長時間にわたるレッスンや、週末に開催される習い事では、お弁当や軽食を持参しなければならないケースもあるでしょう。
共働き家庭では、出勤前の忙しい時間にお弁当を作るのは負担が大きく、帰宅後に作れないことが多いため、毎回準備するのはなかなか難しいものです。また、習い事の時間帯によっては、夕食の代わりにしなければならないこともあり、栄養バランスも考慮しなければなりません。
学校給食のない長期休暇期間中は、さらに大変です。仕事に行く前にお昼ご飯やおやつを準備する必要があり、共働き家庭の保護者負担は大きくなるでしょう。
1-5.大会や発表会への参加が難しい
習い事によっては、定期的に大会や発表会が開催されるため、共働き家庭はスケジュール調整に苦労するかもしれません。特にスポーツや音楽、ダンスなどの習い事では、土日や長期休暇中に大会や発表会が設定されることも多いです。
共働きの場合、週末は平日に片付けられない家事や買い物、病院への通院など、重要な用事が集中しがちです。加えて発表会や大会に参加するとなると、休日の時間が制限されてしまう可能性があります。
特に土日勤務のある保護者は、週末の行事参加は物理的に難しくなります。さらに仕事が忙しい時期と大会や発表会が重なった場合、保護者が十分にサポートできず、子どもが習い事を続けるモチベーションを維持するのが難しくなることもあるでしょう。
2.共働きでも無理なく習い事ができるアイデア7選

共働き家庭では、習い事を続けたくても送迎時間の確保や家庭のスケジュールとの両立が課題となり、断念してしまうケースも少なくありません。しかし、工夫次第で、親の負担を軽減しながら子どもに習い事を続けさせることは可能です。
ここでは、共働き家庭でも無理なく習い事を続けるためのアイデアを7つ紹介します。
2-1.平日は学童保育併設の習い事を選ぶ
放課後の時間を有効活用できる学童保育併設型の習い事は、共働き家庭の強い味方です。具体的には、英会話やそろばん、ダンスなどのレッスンを提供している学童施設があります。
学童保育併設の習い事を選べば、保護者が仕事を終えて迎えに行くまでの時間を有効に使えます。また、学童保育と提携している習い事であれば、友だちと一緒に受講できるため、子どもも楽しみながら学べるでしょう。
共働き家庭では、こうした施設を活用することで、子どもの学びの機会を確保しながら、親の負担を軽減することが可能です。
2-2.送迎サービスのある習い事を選ぶ
送迎サービスを提供している習い事を選べば、保護者の負担を大幅に軽減できます。送迎付きの習い事であれば、自宅や学校の近くまで迎えに来てくれるため、保護者の送迎はいりません。
スイミングスクールや学習塾などでは、指定された場所から送迎バスが出ていることが多く、共働き家庭でも利用しやすい環境が整っています。また、一部のスポーツクラブや音楽教室でも、送迎サービスを提供しているところがあります。
送迎付きの習い事を選ぶときは、送迎エリアや時間帯を確認し、自宅や学校との相性を考えることが大切です。送迎があることで保護者の負担が軽くなるのはもちろん、子どもも安全に習い事に通えるため、共働き家庭にとって非常に有効な選択肢の一つです。
2-3.ファミリーサポートを利用する
ファミリーサポートは、自治体が提供する支援制度です。利用会員と協力会員のマッチングシステムを採用しており、子どもの送迎や一時預かりを地域のサポーターが引き受けてくれます。行政からの補助によって、利用料金が比較的安価なのが特徴です。
また、専門の送迎シッターサービスも選択肢の一つです。子育て支援タクシーは子どもの単独利用が可能で、目的地の入口まで確実に送り届けてくれます。
ただし、ファミリーサポートは、希望の時間帯や場所で協力会員が見つからない可能性もあります。子育て支援タクシーも利用可能なエリアが限定されるため、事前に複数の送迎手段を確保しておきましょう。
2-4.休みの日に習い事をする
共働き家庭では、週末などの休日を利用して習い事をすることで、親子ともに負担を軽減できます。平日が休みの保護者は、その日程に合わせて習い事を組み込むことも可能です。
休日であれば比較的余裕をもってスケジュールを調整できるため、無理なく習い事に付き添えるでしょう。さらに、平日の宿題や学童保育の時間を削らずに済むため、生活リズムが崩れにくいというメリットもあります。
休日の習い事を選ぶ際には、家族全員のスケジュールを考慮し、無理なく続けられる時間帯を選ぶことが大切です。また、休日は家族での予定もあるため、習い事の頻度や時間を調整しながら、家族の時間を確保することも忘れないようにしましょう。
2-5.在宅で完結する習い事を選ぶ
最近では、インターネット環境の発達により、在宅で受講できるオンライン型の習い事が増えています。在宅で完結すれば、送迎の負担はなくなります。また、講師が自宅へ訪問する形式のレッスンも、共働き家庭にとって便利な選択肢の一つでしょう。
オンライン型の習い事の最大のメリットは、親の送迎が不要な点に加え、子どもが自宅のリラックスした環境で学べる点です。レッスンの時間も柔軟に設定できるものが多く、仕事のスケジュールに合わせて習い事の時間を調整しやすいというメリットもあります。
在宅でできる習い事を選ぶときは、子どもが集中しやすい環境を整えることが重要です。また、長時間の画面視聴が負担にならないように、適度な休憩時間を取りながら進めるようにしましょう。
2-6.自宅から近い習い事を選ぶ
子どもが日頃から慣れ親しんでいる通学路沿いや自宅周辺の習い事なら、保護者の送迎なしでも安心して通えるでしょう。学校の校庭や体育館で開催されるサッカーやバスケットボールなど運動系のクラブ活動もおすすめです。
自宅から近い習い事であれば、送迎が必要な場合でも時短になるため、保護者の負担を減らせます。さらに、近隣の習い事であれば、緊急時の対応がスムーズにできるというメリットもあります。
習い事を選ぶ際には、徒歩や自転車で通える範囲にどのような教室があるかを調べましょう。また、体験レッスンを受けて、実際に通いやすいかどうかを確認しておくと安心です。
2-7.祖父母や友人の協力を得る
共働き家庭の場合、祖父母や親しいママ友などの協力を得ることで、習い事を続けやすくなります。祖父母が近くに住んでいる場合は、送迎や付き添いをお願いすれば、負担を大きく減らせるでしょう。仕事の都合で習い事の送迎が難しい日だけサポートしてもらうといった、柔軟な対応も可能です。
また、同じ習い事に通っているママ友の家庭と協力し、交代で送迎を担当する方法もあります。たとえば、週に2回の習い事であれば、1回ずつ交代で送迎することで負担を半減できます。
ただし、祖父母やママ友にサポートをお願いする際には、お互いに無理のない範囲で協力し合うことが大切です。事前に送り迎えの時間やルールを決めておくことで、トラブルを防ぎながらスムーズに習い事を継続できるでしょう。
3.共働きで習い事を続けるための注意点

共働き家庭で子どもに習い事をさせる場合、送迎の負担やスケジュール管理だけでなく、子どもの意欲や成長、家庭全体のバランスを考慮しながら無理のない形で続けることが大切です。
ここでは、共働き家庭が習い事を継続する際に気をつけるべき3つのポイントを詳しく解説します。
3-1.子どもの意見を尊重する
子どもの習い事を決めるときは、保護者の意向だけでなく、子ども自身の意思を尊重することが重要です。「この習い事をやらせたい」と思っても、子どもが興味を持っていなければ、途中で飽きてしまったり、嫌々通うことになったりする可能性があります。
特に共働き家庭では、送迎やスケジュール調整が必要なため、保護者の負担も大きくなりがちです。「せっかく送迎しているのだから、ちゃんと続けてほしい」といった気持ちが生まれると、子どもに無理を強いてしまうこともあるでしょう。
しかし、習い事はあくまで子どもの成長をサポートするためのものであり、本人が楽しんで取り組めることが何よりも大切です。習い事を決める際には、まず子どもとしっかり話し合い、興味のあるものを選ぶようにしましょう。
3-2.目標を明確にする
習い事を始めるときは、何のために通うのか、どのような目標を持つのかを明確にしましょう。目標が曖昧なままだと、途中でモチベーションが下がり、「なんとなく続けているけれど、やる気が出ない」という状態になってしまうことも考えられます。
たとえば、英会話を習う場合、「英語が話せるようになりたい」という漠然とした理由ではなく、「海外旅行で簡単な会話ができるようになりたい」「学校の英語の授業をスムーズに理解できるようになりたい」といった具体的な目標を持たせると、子どももやる気を維持しやすくなります。
目標を明確にすれば、子どもが「なぜこの習い事をしているのか」を理解でき、意欲的に取り組めるでしょう。
3-3.無理を重ねない
習い事の負担が重くなりすぎると、保護者が疲れてしまい、習い事の時間がストレスになってしまう可能性があります。また、保護者の熱心さが子どもへの期待となって表れ、結果的に子どもが無理をしてしまう状況が生まれてしまうこともあるでしょう。
保護者自身が疲れてしまったときや、子どもが負担を感じているときは、習い事を続けるかどうかを見直してみましょう。途中で辞めることに対して罪悪感を持つ保護者も多いですが、無理をして続けるよりも一度休んで見直すことで、よりよい選択肢が見つかることもあります。
習い事は、子どもの成長を促し、将来の可能性を広げるための大切な経験ですが、それと同時に家庭の負担が過剰にならないようにバランスを取ることが重要です。楽しく習い事を続けられるよう、適度なペースで取り組みましょう。
4.共働き家庭の習い事に関するよくある質問

ここでは、共働き家庭が習い事を選ぶときに抱きやすい疑問に回答していきます。ぜひ参考にしてみてください。
4-1.何歳から一人で習い事に行ける?
一般的に、小学校低学年のうちは親の送迎が必要なことが多く、高学年になると一人で通えるようになるケースが増えてきます。ただし、子どもの性格や習い事の場所、周囲の環境などによって状況は異なるため、一概に「何歳から大丈夫」とは言い切れません。
一人で習い事に行けるかどうかを判断する際には、以下の点を考慮するとよいでしょう。
- 習い事の場所が自宅から近いか
- 交通手段が安全か
- 時間帯が遅すぎないか
一人で通わせる場合は、万が一のトラブルに備えて、子どもとの連絡手段を確保しておくことも重要です。スマートフォンやキッズ携帯を持たせたり、習い事の先生と緊急時の対応を話し合ったりして、安全対策を徹底しましょう。
4-2.人気の習い事は?
習い事は子どもが興味を持って楽しく続けられるかどうかが大切ですが、人気のある習い事としては、大きく以下のカテゴリーに分けられます。
スポーツ系の習い事
- スイミング
- サッカー・野球
- ダンス
文化・芸術系の習い事
- ピアノ
- 絵画・書道
学習系の習い事
- 英会話
- そろばん
- プログラミング
昔から定番であるスイミングやピアノなどに加えて、グローバル化が進む現代では、英会話もおすすめです。学校教育でも英語の授業が低年齢化しており、早いうちから英語に親しんでおくことは、子どもの将来にとって大きなメリットとなるでしょう。
5.共働きでも無理なく習い事を続ける環境を整えよう

共働き家庭では、時間的な制約や送迎の負担などの問題から、子どもの習い事を続けることが難しいケースがあります。しかし、学童保育と連携した習い事や送迎サービスの利用、オンラインレッスンの活用など、工夫次第で習い事を無理なく続けられます。また、子ども自身が楽しめる習い事を選ぶことも、継続のための重要なポイントです。
特に、これからの時代に必要なスキルの一つとして、英語力の向上が注目されています。英会話スクールはもちろん、自宅で学べるオンラインレッスンなど、さまざまな方法で英語に触れる機会があります。
「英語を学ぶ」のではなく、「英語を自然に身につける環境」を求めるなら、英語で預かる学童保育・プリスクール「Kids Duo(キッズデュオ)」がおすすめです。Kids Duo(キッズデュオ)は、子どもたちが英語環境で過ごすことをコンセプトにした学童保育・プリスクールです。
平日に英語を習得できる環境で過ごすため、休日の家族の時間を邪魔せず無理なく習い事を続けられます。さらに小学校からKids Duo(キッズデュオ)へは巡回送迎があり、共働き家庭でも負担なく安心して通えます。
習い事と学童の両立を考えている方は、ぜひKids Duo(キッズデュオ)の無料体験にご参加ください。共働き家庭だからこそ、子どもが楽しく成長できる環境を整え、無理なく習い事を続けられる方法を選びましょう。
執筆者:英語で預かる学童保育Kids Duo
コラム編集部